| 事例名称 |
重油脱硫装置加熱炉の火災 |
| 代表図 |
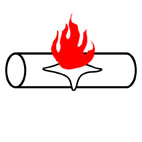
|
| 事例発生日付 |
2004年04月22日 |
| 事例発生地 |
茨城県鹿島郡神栖町 |
| 事例発生場所 |
鹿島石油株式会社鹿島製油所 |
| 機器 |
第1重油脱硫装置は1984年3月に完成した。第1重油脱硫装置反応系のフローシートを図2に、設計条件を表1に示す。
(1)原料である重油は原料ポンプ(PU-201)で昇圧され、熱交換器(HE-205)で予熱された後、水素が加えられ、加熱炉(FU-201B)に入る。加熱炉で約385℃まで加熱された後、反応塔(RT-202A1/A2,B1/B2)に入り、触媒により脱硫反応が行われる。加熱炉にはNo.1~No.4の4本のコイルがあり、それぞれに原料が張り込まれ、出口で2系列に合流して反応塔のA系列(No.1,2コイル)、B系列(No.3,4コイル)に送り込まれる。
(2)反応塔を出た流体は熱交換器(HE-206)で約360℃に降温され、高温分離槽(VE-202)に入り、ガス分と液分に分離される。液分は精留系へ送られ、ナフサ、軽油、重油に分離される。
(3)高温分離槽(VE-202)で分離されたガス分は熱交換器(HE-205,207,208)等を経て約50℃に冷却された後、低温分離槽(VE-203)でガス分(水素)と液分に分離される。液分は精留系へ送られる。
(4)低温分離槽(VE-203)で分離されたガス分はリサイクルコンプレッサー(CP-201)で昇圧され、メイクアップコンプレッサー(CP-202)から補給される水素と一緒になって、加熱炉の入口に戻され、再び原料油に加えられる。 |
| 事例概要 |
4月21日午前5時2分頃、地震のような地響きがすると同時に、計器室操作パネルの警報が一斉に鳴り、ほとんどの警報ランプが点灯した。直ちに係員が現場確認のため計器室を出たところ、加熱炉FU-201B東側に火柱が見えたため、計器室に戻りプラントの緊急運転停止を指示した。
火災現場では火災発生装置の降圧を行うとともに、火災発生装置以外の全装置も午前5時7分に緊急運転停止を行った。人的被害なし。 |
| 事象 |
火災の原因は、加熱炉加熱管No.4コイルの4段目にコーキング*が発生し、局部的な温度上昇に伴うクリープ損傷が起こり、亀裂が進展、高圧の内圧により加熱炉管が大きく開口すると共に炉内に漏洩した重油及び水素の混合物が着火したものである。
火災鎮火に至る消火方針については、可燃物が系内に残存する状態で消火することは再び着火する等の2次火災を引き起こす恐れがあること及び火災が加熱炉内であるため周囲への延焼の危険は少ないと判断し、発災箇所の上下流を遮断して燃焼しているものを燃え尽きさせることとした(図3参照)。なお、周辺設備に対しては熱影響を考慮し大型化学消防車等で冷却散水を実施した。
この結果、発災から約53時間後の4月23日午前10時10分、鎮火を確認した。
事故の起点となった加熱炉の開口部の損傷形状については、一般的に、このような開口形状をフィッシュマウス状の開口と呼んでおり、高圧の内圧による配管等の噴破によって生じる場合に認められるものである(図4参照)。
破面近傍のミクロ組織観察の結果、クリープ変形に起因すると考えられる粒界亀裂が認められ、一部結晶粒内にもクリープ変形による亀裂と想定されるボイドの存在が確認された。亀裂が結晶粒の内部にも存在したことから、比較的高温で短時間のクリープであったと推定された。
最大開口部から下流に200mmの部位の破面観察を行った結果、延性破壊の破面が認められた。
開口サイズは、管軸方向510mm、円周方向 325mmであるが、事故時の系内圧力低下記録から計算すると、当初は直径190mm程度と推定され、開口した後現状の形状まで押し拡げられたと考え得る。また、開口方向は火炎側45度下向きで、また加熱管は開口部を軸に開口面を谷側とする曲げ変形が認められ、これは噴破時に生じた反力によるものと推定される。
*コーキング
ここでいうコーキングとは、加熱された原料油中の重縮合物質等が加熱炉管内表面でコークス化して付着することを指す。
コーキングは、石油精製装置の加熱管、精留塔内部などの高温部で発生し、コークス層の増大に伴って、熱効率の低下、高温クリープ損傷、侵炭、閉塞といったトラブルの原因となる。
一般的には、重質なアラビアンミディアム原油より軽質なオマーン原油等がコーキングしやすい傾向にあるといえるが、原料油中のアスファルテンも影響するといわれている。 |
| 経過 |
下記に示す経過をたどって発災したと想定。
(1)加熱管にコーキングの発生
(2)コーキングの局部的成長
(3)加熱管表面温度の上昇
(4)加熱炉の偏りのある運転
(5)クリープ損傷の発生
(6)開口しプロセス流体の漏洩
(7)加熱炉の炉壁の損傷
(8)加熱炉内外の火災発生 |
| 原因 |
調査結果から、事故の経過は次のとおりと推定した(図6参照)。
(1)加熱管にコーキング発生
加熱管内でコークの薄膜が生成、運転停止開始の温度変化を経て層状のコークとして経年的に付着蓄積されていた。
(2)コーキングの局部的成長
蓄積されるコークは位置及び内面形状などにより均一な成長ではなく表面温度の上昇と相俟って局部的に成長した。
(3)加熱管表面温度の上昇
加熱管内表面に付着蓄積されたコークにより内部流体への熱伝達が悪くなり、コークの厚みが増すにつれ加熱管外表面温度が上昇し、結果としてコーキングを局所的に進行させた。
(4)加熱炉の偏りのある運転
加熱炉センターウォールで区分されたA系列とB系列で処理量が異なり、B系列の処理量が多く、従ってB系列の燃料使用量が多くなっていた。さらに、B系列に10本あるバーナーの燃焼負荷が中央部に偏っていたため、中央部で火炎が伸延し、4段目付近の温度が上昇していた。
(5)クリープ損傷の発生
B系列4段目中央部の温度が著しく上昇し、時間経過とともに加熱管の熱応力クリープによる損傷が内面から進行した。
(6)加熱管が開口しプロセス流体の漏洩
クリープ損傷の進行によりプロセス流体の圧力に伴って開口が生じ、この破面から、高温・高圧条件のプロセス流体が噴出した。噴出時の圧力で開口部を押し拡げ、開口部の面積がフィッシュマウス状に拡大した。
(7)加熱炉の炉壁損傷
加熱管から炉内に放出されたプロセス流体の圧力(動圧)で加熱炉のエンドパネル(炉壁)に大きな開口が生じた。
(8)炉内外火災の発生
炉内に放出されたプロセス流体は、加熱炉のエンドパネル等から炉外に流出して炉外火災が発生した(図5参照)。さらに、炉内のセンターウォールが噴出したプロセス流体の圧力で倒壊したことに伴い、センターウォールの材料であるレンガの倒壊により炉床が大きく損傷し、そこから空気が炉内に入り、炉内の火災を拡大させた。 |
| 対処 |
発災した加熱炉は、原料である重油を原料ポンプで昇圧し、予熱の後に水素が加えられ、重油+水素の混合流体として加熱炉に入り加熱した後に脱硫反応させるプロセスとなっている。このように水素を添加した加熱炉は、高圧状態で加熱するため、石油精製関係者の間では、一般的にコーキングが起こり難いということで知られていた。
コーキングの検査も2年に一度放射線透過試験で確認していたが、実際には、検査点と実際のコークの発生ポイントが違っていたため、発災まで発見に至らなかったものであった。
(1)平成12年(前回デコーキング)以降の操業において加熱管内壁にコークが蓄積していたが、それを把握できなかった。
(2)反応塔の触媒層差圧の影響からB系列に偏った負荷をかけており、B系列の燃料ガス使用量が増加していた。
(3)加熱炉のB系列のバーナー負荷が中央部に偏っており、火炎の伸張、熱負荷の増大が生じていた。
これらの要因が重なって、加熱管が高温クリープ損傷で噴破したものと推定された。 |
| 対策 |
(1) 加熱管内壁のコーク付着状況の把握と除去
(a)コーキング検査部位の見直し
コーキングの発生状況を確認するため定期的に検査を行っていたが、測定点がコーキングを生じやすい部位となっておらず、把握することができていなかった。今回の燃焼解析結果およびコーキング調査結果に基づき、コーキング発生の可能性の高いと想定される部位に測定点を変更する。
(b)デコーキングの実施
デコーキングを一定周期で実施し、その結果に基づきコーキング検査部位の妥当性の評価・見直しを行い、デコーキングを行う周期に反映させる。
(2) 加熱炉管理の適正化
(a)加熱管表面温度計の増設
今回の燃焼解析結果およびコーキング調査結果に基づき、コーキング発生の可能性の高いと想定される部位に増設する。
また、加熱炉上部についても東と西の2ケ所では中央部の把握ができないため、今回、中央部にも増設し加熱管表面温度監視とともに炉内の均一な加熱を可能とする。
(b)炉内監視テレビの新設
運転員が定期的な巡回点検で、バーナー火炎の状況および加熱管に発生する異常の有無を目視で確認していたが、炉内監視テレビを新設し計器室での連続監視を可能とし、監視を補完強化する。
(c)加熱炉負荷の管理
加熱炉のA系列とB系列の炉内条件を均等化するため、処理量差の上限管理を行い、管理値はコーキング検査結果およびデコーキングの実施結果により評価・見直しを進める。
(d)バーナーに個別圧力計の設置
加熱炉の全バーナーに圧力計を設置し、バーナー毎の燃料ガス使用状況を把握してバーナーの均等使用を可能とする。 |
| 知識化 |
コークの生成は、付着量の多少はあるものの加熱管内壁全面で発生する現象である。近年発生した加熱炉の事故は、全ての事例において、加熱炉管が局所的に高温となった場合、加速的にコークの生成が進んだ結果、クリープ損傷により開口しプロセス流体が漏洩・火災となっている。
加熱炉の運転管理としては、通常運転時はもちろんのこと運転条件の変更等による加熱管壁の温度管理には特段の注意を払うことが重要となってくる。 |
| 背景 |
FU-201Bの最近3年間の検査履歴を表2に示す。
加熱管の放射線透過検査によるコーキング検査は、コーキングの有無を確認するためほぼ2年毎に抜き取りで実施している。
2000年の検査時には、1984年に加熱炉を設置して以来、初めてコーキングが確認(No1コイルとNo4コイルの最下段部)されたため、ピグによるデコーキングを実施した。
デコーキングによるスケールの排出状況は、厚さ1~5mmの硬いスケールが少量出た程度であった。
それ以降、2002年、2003年に実施した放射線透過検査では、コーキングは確認されていない。 |
| 後日談 |
炉外の火災が鎮火した後も、炉内で火災が長時間続いていた原因を究明するため実験により検証を行っている。
脱硫触媒、アルミナボールと重油を充填した実験装置で、事故発生時の反応塔と同じ温度に保持した結果、充填塔内で分解反応が生じ、軽質炭化水素を主成分とする分解ガスが生成することが確認できた。
この結果から、事故時においても反応塔(RT-202A1,A2,B1,B2:4基)内で重油の分解反応が生じ、生成した分解ガスが加熱炉に流入し、加熱管の破損部から放出されて燃焼が続いていたためと結論づけた。 |
| シナリオ |
| 主シナリオ
|
組織運営不良、管理不良、設備管理不良、誤判断、誤った理解、水素添加、コーキングなし、使用、保守・修理、劣化予測、検査点、使用、運転・使用、反応器負荷、運転変更、バーナー片炊き、不良現象、熱流体現象、コーキング、クリープ、不良現象、化学現象、反応継続、長時間火災、破損、破壊・損傷、高圧、開口、フィッシュマウス、二次災害、損壊、漏洩、火災
|
|
| 情報源 |
第1重油脱硫装置の加熱炉事故調査委員会報告書 2004年7月
|
| 死者数 |
0 |
| 負傷者数 |
0 |
| 社会への影響 |
我が国全体の石油精製能力の見直しにより、発災製油所と同じグループ企業の製油所(愛知県)が石油精製を止めたこと、並びに、2003年9月26日に発生した十勝沖地震において、地震により損傷を受けた製油所の生産が止まっていた状況下でこの事故が発生した。このため、一時的に石油製品の需給バランスが崩れ、重油等の値段が徐々に値上がりするといった影響も出はじめた矢先、イラク原油の供給不安定をきっかけとしたOPEC原油の急騰に伴って、石油製品全体の値上げが必至とされており、これらの値上げが実施されると、上向き加減となってきた我が国の景気にとっても大きな打撃となることが懸念されている。
最近の加熱炉のコーキングによる事故事例は、この事故の他、1996年6月に直接脱硫装置の加熱炉(沖縄県)及び2003年4月に間接脱硫装置の加熱炉(北海道)で発生している。3つの事故のプロセスはそれぞれ違っており、発災した加熱炉は、炭化水素と水素を混合させて加熱するタイプのものであった。このようなプロセスの加熱炉は、一般に加熱管内壁でのコークの生成は進展し難いと理解されており、現実に多くの加熱炉で深刻なコーク堆積は殆ど問題になっていないものであったが、石油業界では、同じようなタイプの加熱炉の維持管理に少なからず問題を提起した事故であった。 |
| マルチメディアファイル |
図2.第1重油脱硫設備反応系の概略フロー
|
|
図3.発災後の加熱炉の外観
|
|
図4.フィッシュマウス状の開口
|
|
図5.大きく開口したエンドパネル
|
|
図6.フォールトツリー図
|
|
表1.加熱炉の設計条件等
|
|
表2.検査履歴
|
| 分野 |
材料
|
| データ作成者 |
赤塚 広隆 (高圧ガス保安協会)
小林 英男 (東京工業大学)
|