| 事例名称 |
低密度ポリエチレン製造装置におけるアセトン注入バルブグランド部からエチレンの漏洩 |
| 代表図 |
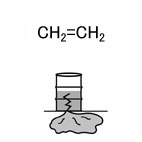
|
| 事例発生日付 |
1999年04月25日 |
| 事例発生地 |
神奈川県 川崎市 |
| 事例発生場所 |
化学工場 |
| 事例概要 |
低密度ポリエチレン製造装置(別名高圧法ポリエチレン)の二次昇圧機の吸入側配管に、アセトンを注入するためバルブを開けようとした。バルブハンドルとステム部を固定するロックボルトが緩んでいてハンドルが空回りをした。パイプレンチで直接ステムをつかみ、バルブを開けた。過大な力が、バルブのグランドナットにかかりグランドナットが外れ、エチレンガスが噴出した。 |
| 事象 |
低密度ポリエチレン製造装置のエチレンガスの二次昇圧機吸入側に接続されているアセトン注入用のバルブを開けていた。そのとき、酢酸ビニルを含んだエチレンガスがバルブグランド部より噴出した。作業員は顔面に軽傷を負った。図2参照 |
| プロセス |
製造 |
| 単位工程 |
仕込 |
| 単位工程フロー |
図3.単位工程フロー
|
|
図4.単位工程フロー
|
| 物質 |
エチレン(ethylene)、図5 |
| 酢酸ビニル(vinyl acetate)、図6 |
| 事故の種類 |
漏洩 |
| 経過 |
1999年4月25日14:00頃 アセトン注入ラインを開ける指示があり、2ヶあるラインのうち1ヶ所の注入バルブを回したが空回りした。
14:18 ハンドルが空回りしたため、バルブのステムをパイプレンチでつかみ回していた。
突然バルブグランド部から酢酸ビニル混じりの高圧(1.35MPaG)のエチレンガスが噴出した。
この時作業員が顔面を負傷した。
14:19 負傷した作業員が計器室に駆けつけ、緊急停止を指示した。
14:20 噴出は停止した。
バルブのステム: バルブ内弁を上げ下げさせる軸のことで、上部に回転させるハンドルが付いている。 |
| 原因 |
1.バルブハンドルが空回りしたので、バルブステムをパイプレンチで直接掴んで回したため、バルブのグランドナットが外れてエチレンガスが噴出した。
2.空回りの原因は、ハンドルとステムを固定している六角のロックボルトが緩んでいたためである。ロックボルトを締め付ける六角ナットが見つからず、作業の時間が迫っていたため、直接パイプレンチを使用しバルブを開けようとした。 |
| 対処 |
装置を停止して、被害の拡大を防いだ。 |
| 対策 |
1.バルブハンドル用の六角レンチの置き場をわかりやすく表示した。
2.グランドナットストッパーの厚みを0.8mmから2.0mmに変更した。
3.バルブのハンドルを棒状のものから丸型のものに変更する。
4.全従業員にバルブ操作時の工器具の使用禁止を周知徹底する。
5.全従業員にバルブの構造、取り扱いについて再教育を実施した。
6.作業基準および管理基準の見直しをした。 |
| 知識化 |
問題のあるものを放置しておくと事件が起こる(この場合は棒状のハンドルが空回りしやすいことが問題)。事故防止には先手を打つことが重要である。 |
| 背景 |
1.バルブハンドルが空回りしやすいタイプであった。発災したバルブハンドルは棒状であったが、丸型のハンドルの方が良い。
2.判断ミスがあった。アセトンの注入開始予定時間が迫っていたので、安全にロックボルトを締め付けてから注入するか、危険を承知でパイプレンチを使用して直ぐに注入を開始するかの判断であったが、パイプレンチを使用する方を選んだ。
<間接的には、以下の2点が考えられる>
3.空回りしやすいことが分かっていたのだから、判断基準あるいはマニュアル上で、その時の対応を規定しておく必要があった(例えば、作業時間が迫っていても、パイプレンチは使わず、ロックボルトの締め直しを優先するといったように)。
4.ロックボルトを締め付ける六角レンチがバルブの側になかったことである。作業上で必要な物を必要なときに使うことができるようにする現場管理が不十分だった。
3と4は単なるヒューマンエラーで片付けるのではなく、管理面についても考えるべき問題がある。 |
| よもやま話 |
☆ 小口径のバルブの開閉には、サイズに対応したハンドル回し以外は使ってはならないが、バルブ取扱者の常識である。しかし、パイプレンチや延長パイプを使ってバルブハンドルを壊したり、ステムをねじ切るようなトラブルがかなり起こっている。教育以外に何かいい方法はあるであろうか(ここのバルブはおそらく3/4あるいは1インチの小口径バルブだろう)。 |
データベース登録の
動機 |
小口径バルブの不適切な取り扱いの例 |
| シナリオ |
| 主シナリオ
|
組織運営不良、管理不良、管理の緩み、不注意、理解不足、リスク認識不良、計画・設計、計画不良、設計不良、不良行為、規則違反、安全規則違反、破損、破壊・損傷、バルブ破損・漏洩、身体的被害、負傷、1名負傷
|
|
| 情報源 |
川崎市消防局予防部保安課、川崎市コンビナート安全対策委員会資料(1999)
|
| 負傷者数 |
1 |
| 物的被害 |
エチレン106kg、酢酸ビニル28L噴出 |
| 被害金額 |
51000円(川崎市コンビナート安全対策委員会資料) |
| マルチメディアファイル |
図2.噴出状況図
|
|
図5.化学式
|
|
図6.化学式
|
| 分野 |
化学物質・プラント
|
| データ作成者 |
小林 光夫 (東京大学大学院 新領域創成科学研究科 環境学専攻、オフィスK)
田村 昌三 (東京大学大学院 新領域創成科学研究科 環境学専攻)
|