| 事例名称 |
手違いによる停止中の酸化エチレン付加物製造装置の火災 |
| 代表図 |
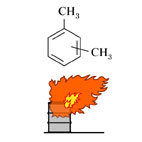
|
| 事例発生日付 |
1987年12月10日 |
| 事例発生地 |
神奈川県 川崎市 |
| 事例発生場所 |
化学工場 |
| 事例概要 |
停止中の酸化エチレン付加装置で、キシレンが廃水タンク上流のドラムから廃水タンクへ調節弁内漏れのため流入した。そのキシレンがオーバーフローし、側溝に流入した。他のタンクをパージのため使用したスチームとそのドレンが側溝に流入し、その高温でキシレンが気化し、溶接スパークで着火した。調節弁だけでの閉止は漏れの原因になり、容器の大きさの差からオーバーフローした。また、火気使用場所での安全管理が不十分であった。 |
| 事象 |
生産調整で停止している装置の廃水タンク(図2のD-7303B)に他装置の廃水タンクからの受入配管の取付けをしようとした。電気溶接に先立ち、溶接器のホールダーに溶接棒をセットし、近くの柱のブレースに接触させアースを確認した。その火花で漏洩キシレンの蒸気が着火した。 |
| プロセス |
製造 |
| 単位工程 |
設備保全 |
| 単位工程フロー |
図2.単位工程フロー
|
| 物質 |
キシレン(xylene)、図3 |
| 事故の種類 |
漏洩、火災 |
| 経過 |
当該装置は生産調整のため、1987年11月7日から停止していた。
1987年12月10日 発災した廃水タンクへ別装置の廃水抜出し管の接続を計画した。
同日08:30頃 運転担当者が現場を確認したが、異常はなかった。
13:00~13:20 協力会社員が溶接機のアースを取り付けた。
13:25 配管取り付けのため溶接機のホルダーに溶接棒をセットし、溶接準備作業に入った直後に火災が発生した。 |
| 原因 |
1.火気使用工事に先立って、安全確認をしていない。停止装置とはいえ、近傍に可燃物がある装置での安全確認は当然の措置であろう。
2.当該装置の停止時に、廃水タンクの上流にあるドラムにキシレンを残して停止した。調節弁だけで閉止したが、調節弁が内漏れし、キシレンが廃水タンクに洩れ込み、廃水タンクベント線より溢流した。図2参照。
3.キシレンがタンクをオーバーフローして、危険物があることを想定していない側溝に流入した。
4.同じ側溝に他のタンクをスチームパージしたスチームとドレンが流入し、その熱でキシレンが気化した。
5.直近で溶接工事をした。 |
| 対処 |
注水消火 |
| 対策 |
1.協力会社入構者の安全教育を行う。
2.火気使用作業でのガス検知の実施を確実に行う。
3.薬剤タンクの液面管理が可能な設備にする。 |
| 知識化 |
1.自動調節弁(コントロールバルブ;CV)は通常、全閉にしても流れを遮断することはできない。CV1ヶで閉止できると考えてはならない。流れを遮断する時の大原則である。
2.複数の容器が連結されている場合は誤漏洩や、誤流入の可能性を認識すべきである。 |
| 背景 |
1.調節弁だけで流れが遮断できると思った。停止時にキシレンをドラム内に残して停止した。さらにそのドラムから発災タンクの接続配管は調節弁一つで閉止されていた。そのため、キシレンが発災タンク側に漏洩した。通常、調節弁は完全閉止できるようには設計製作されていない。
2.廃水タンクと上流のドラムの大きさおよび上流のドラムに残したキシレン量から、バルブ漏洩したら発災タンクをオーバーフローするのは明らかである。定量的な考え方をしていない。液面管理もしていない。
3.火気使用工事に対する危険認識が低い。装置が停止していても、可燃物が装置に残っていれば、火気使用時の危険性は運転時とほぼ同じであろう。
4.改修工事を行う協力会社側に危険物が存在するという注意が伝わっていない。
全体に危険認識が少ないのが、要因ではないかと推測する。 |
| よもやま話 |
☆ 装置では、CVだけにかぎらず、バルブは洩れては困る時に洩れることがよくある。完全に漏れをなくすなら、バルブだけに頼ってはならない。 |
データベース登録の
動機 |
可燃物の近傍での火気使用に伴う典型的事故例 |
| シナリオ |
| 主シナリオ
|
価値観不良、安全意識不良、安全対策不足、組織運営不良、管理不良、作業管理不良、不注意、注意・用心不足、作業者不注意、計画・設計、計画不良、設計不良、不良行為、規則違反、安全規則違反、不良現象、化学現象、蒸発、二次災害、損壊、火災、身体的被害、負傷、負傷1名
|
|
| 情報源 |
全国危険物安全協会、危険物施設の事故事例100(1991)、p.14-15
高圧ガス保安協会、石油精製及び石油化学装置事故事例集(1995)、p.169-174
|
| 負傷者数 |
1 |
| 物的被害 |
モーター,天井裏若干,ビニールシート焼損.キシレン約480リットル焼失. |
| 被害金額 |
推定800万円(石油精製及び石油化学装置事故事例集) |
| マルチメディアファイル |
図3.化学式
|
| 備考 |
溶接工事時の事故。 |
| 分野 |
化学物質・プラント
|
| データ作成者 |
若倉 正英 (神奈川県 産業技術総合研究所)
田村 昌三 (東京大学大学院 新領域創成科学研究科 環境学専攻)
|