| 事例名称 |
ポリプロピレン製造設備のバルブの誤開放によるサンプリング中の火災 |
| 代表図 |
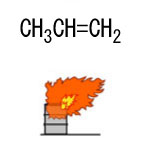
|
| 事例発生日付 |
1996年03月08日 |
| 事例発生地 |
大分県 大分市 |
| 事例発生場所 |
化学工場 |
| 事例概要 |
通常運転のポリプロピレン製造装置で火災があった。反応器出口でのポリプロピレンのサンプリング時に同時に2つのバルブを開にして大気中にプロピレンとポリプロピレン粒子を放出した。結果的にはヒューマンエラーであるが、ヒューマンエラーを起こし難くするための、フェールセーフ、フールプルーフの考え方が浸透していないのが問題である。同時に現場管理にも手抜かりがあったのではないか。 |
| 事象 |
ポリプロピレン製造装置の反応器出口でのサンプリングに際し、バルブ操作のミスによって火災が発生した。 |
| プロセス |
製造 |
| 単位工程 |
反応 |
| 単位工程フロー |
図2.単位工程フロー
|
| 反応 |
重合・縮合 |
| 物質 |
プロピレン(propylene)、図3 |
| ポリプロピレン(polypropylene)、図4 |
| 事故の種類 |
火災 |
| 経過 |
通常運転中に、反応器出口での生成ポリマーのサンプルを採取するために作業員が5階の脱ガス槽の弁を開けるエアー式自動弁のハンドルを「開」にした。そのとき、4階にあるサンプリングポット下部から火災が起こった。この段階では、まだ「閉」であるべき4階のサンプリングポット下部の弁が「開」になっていた。図2参照
脱ガス槽: 重合反応器出口に設置され、未反応のプロピレン主体のガスと生成したポリプロピレン粒子を分離する容器。
サンプリングポット: 脱ガス槽下部に設置されているサンプリング用の小さな容器。粉体のポリプロピレンに同伴する未反応ガスを分離してポリプロピレンだけを採取する。 |
| 原因 |
当反応器出口では、生成したポリプロピレン粒子と未反応のプロピレン蒸気が共存する。蒸気とポリマー粒子をほぼ反応器と同じ高圧の脱ガス槽で分離して、下部からポリプロピレン粒子を抜き出す。高圧のため、ポリマー粒子はいまだにプロピレン蒸気と一緒である。その状態のポリマー粒子のサンプリングは一度サンプリングポットに受け、共存する蒸気を脱圧してパージする。
サンプリングを行う際、作業員がサンプリング前の準備の最終作業であるサンプリングポット底部にあるサンプリング弁の「閉」であることの確認を怠り、サンプリングポットの入り口弁を開けて、採取作業に入ったため、脱ガス槽からサンプリング弁を通じてポリプロピレン樹脂とプロピレンガスが噴出し、粒子およびガスにより生じた静電気により着火したものと推定される。 |
| 対処 |
初動措置として、CCRにて緊急停止操作を行った。現場では固定消火設備による散水、発災箇所の縁切り作業、窒素封入を行った。さらに自衛消防および共同防災隊で高所放水車、大型化学車2台28人で冷却放水を行った。
CCR: Central Control Roomの略で、装置の中心的な計器室あるいは制御室をいう。 |
| 対策 |
1.通報の遅れに対する通報体制の見直しを図る。
2.サンプルポット下部の弁が「閉」でない限り、脱ガス槽下部の弁は開閉しないよう構造に設備改善する。 |
| 知識化 |
確認ミスを100%無くすことは難しいが、フェールセーフ、フールプルーフ技術の導入で、エラーを起こさない、あるいはエラーを起こしても事故に結びつかないシステムを考えることが重要である。 |
| 背景 |
1.思い込みによるヒューマンエラーであろう。確認すべきバルブの開閉を、いつも閉まっているはずのバルブだからとして、確認しなかったと思われる。ただし、サンプリングポットのサンプル弁が閉まっていない限り、サンプリングポット入り口のエアー弁を開けさせないインターロックを設置すれば、簡単に安全対策ができる場所ではある。
2.少し不思議なのは、プロセスと大気の縁切りバルブは通常「閉」で管理するのではないだろうか。この事例ではサンプリングポットの底部バルブはまさにそれにあたる。通常「開」では、上流側のバルブの内漏れか、誤操作で開にすれば必ず漏洩する。運転管理面の手抜かりはなかったであろうか。 |
| よもやま話 |
☆ この事故の原因はヒューマンエラーだが、誤操作があっても事故を起こさないように配慮したプロセス設計が重要であり、これはそれが行われていない良い例である。 |
データベース登録の
動機 |
単純なバルブ操作ミスによる事故例 |
| シナリオ |
| 主シナリオ
|
価値観不良、安全意識不良、安全対策不足、不注意、注意・用心不足、作業者不注意、手順の不遵守、手順無視、操作手順無視、計画・設計、計画不良、シーケンス構成不良、不良行為、規則違反、安全規則違反、二次災害、損壊、漏洩・火災
|
|
| 情報源 |
消防庁、危険物に係る事故事例‐平成8年(1997)、p.438-439
消防庁、KHKだより、特集号(1997)、p.33-35
|
| 死者数 |
0 |
| 負傷者数 |
0 |
| 物的被害 |
4階ガスクロ室の建家と分析機器類焼損. |
| マルチメディアファイル |
図3.化学式
|
|
図4.化学式
|
| 備考 |
WLP関連教材
・プラント機器と安全-運転管理/運転管理と安全概論 |
| 分野 |
化学物質・プラント
|
| データ作成者 |
新井 充 (東京大学大学院 新領域創成科学研究科 環境学専攻)
田村 昌三 (東京大学大学院 新領域創成科学研究科 環境学専攻)
|