| 事例名称 |
ポリプロピレン製造装置の重合槽において遠隔操作弁の遠隔操作による爆発 |
| 代表図 |
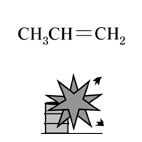
|
| 事例発生日付 |
1973年10月08日 |
| 事例発生地 |
千葉県 市原市 |
| 事例発生場所 |
化学工場 |
| 事例概要 |
1973年10月8日 ポリプロピレン製造装置の複数基ある重合槽の1基が冷却器洗浄の作業を行っていた。引き続き他の1基が洗浄作業に入った。その後工場に停電が起こり、後から停止した反応器の遠隔操作弁を開こうとして、誤って先に停止していた方の反応槽の遠隔操作弁を開いた。遠隔操作弁の先が工事のため大気開放になっていたため、大量のプロピレン、ヘキサンなどが流出し、大爆発になり、4名が死亡した。 |
| 事象 |
ポリプロピレン製造装置で停電時に大爆発が起こった。複数基ある重合槽の内2基に付帯する補助冷却器の洗浄を行っていた。この時停電があった。バルブ操作のミスにより、一方の重合槽から大量の液化プロピレンが漏洩して、数分後、これに着火したため大爆発が起こり、続いて火災となり、東西約100m余り、南北約300mの間の工場設備が焼失して、4人が死亡した。図2参照
補助冷却器:発熱反応を制御するため、重合槽外部に設けた熱交換器で重合槽底部からポンプで反応液を供給し、冷却された液を重合槽上部から戻すことで温度制御する。ただし、図3では補助冷却ラインと記されている。 |
| プロセス |
製造 |
| 単位工程 |
設備保全 |
| 単位工程フロー |
図3.単位工程フロー
|
|
図4.単位工程フロー
|
| 物質 |
プロピレン(propylene)、図5 |
| ヘキサン(hexane)、図6 |
| 事故の種類 |
漏洩、爆発・火災 |
| 経過 |
1973年10月8日 事故当日は、朝から6号重合槽の補助冷却器の洗浄作業が行われていた。重合槽から補助冷却器へ供給する循環ポンプへの配管上の遠隔操作の遮断弁は閉止していたが、重合槽と冷却器を結ぶフランジ部が取り外され、さらにフランジ部手前の循環ポンプのサクション弁は開放されていた。反応器は遠隔操作弁一つで外気と遮断されている状態だった。
21:55頃 4号重合槽の補助冷却器が不調のため洗浄作業が開始されていた。補助冷却器を切り離すため、遠隔操作の遮断弁は閉止された。
22:01頃 工場内の変圧器の開閉器絶縁油劣化のため停電となった。そのため、4号重合槽への洗浄用溶剤の注入を停止し、出口の遠隔遮断弁を開放しようとした。停電でパネル盤が暗く、誤って6号重合槽出口の遠隔遮断弁を開放した。6号重合槽内容物(60℃、1kPa、液化プロピレン5.4トン、ポリマー8.8トン、ヘキサン26トン)の大部分が漏洩した。漏洩により気化したプロピレン蒸気は工場内に拡散した。
22:07頃 重合槽の位置から南方約60mのところにあるペレット工場を中心にガス爆発が起こった。火災に遷移した。
なお、重合槽への原料供給を減らせば、補助冷却器を切り離しても運転できるので、洗浄作業は補助冷却器を重合槽から切り離すだけで、重合は続けていた。 |
| 原因 |
4号機の遠隔遮断弁を閉止するつもりが、6号反応器の出口側遠隔遮断弁を誤って開放したため漏洩が起こり、大量のプロピレン蒸気が工場内に拡散した。ペレット工場内の電気火花等により着火が起こり、大規模なガス爆発が起こった。 |
| 対策 |
再発防止対策としては、以下の点が考えられる。
1.停電時もパネルの照明を維持する。
2.パネル上のコックの配置を、誤操作しにくいよう工夫する。
3.バルブ一つでの大気との縁切りを避け、仕切り板を挿入する。
4.修理作業中に、開放が危険な弁には、開放しないようロックをする。 |
| 知識化 |
1.間違えにくい操作系のパネル配置や、停電時の照明の確保などは検討が必要である。修理中には操作を不可能にする措置が必要である。
2.遠隔操作弁一つでの大気との遮断は絶対に避けねばならない。 |
| 背景 |
1.漏洩の発生要因は、6号重合槽の遮断弁を誤って開放したことである。これには、全ての重合槽の遮断弁の操作用コックが一つの現場パネルにあり、その現場パネル盤が停電のため暗かったこと、およびパネル盤上のコックの間違えやすい配置という背景となる要因がある。また、遠隔操作弁は色々な理由で開くことがあり、大気開放時等は仕切り板を挿入すべきである。以上、安全工学的配慮に欠けるパネル設計と運転の慣れに起因する工事計画の不適切による事故であると推定する。さらに、遠隔操作弁と合わせて直列二重化になる循環ポンプのサクション弁が開いている。サクション弁と遠隔操作弁間の水洗浄の乾燥のため開いていたようである。本来は乾燥終了後にすぐに閉めるべき弁である。
2.遠隔遮断弁の操作には作動用空気配管の計器室と現場パネルの2ヶのコックを開にする必要がある。安全維持のための二重化と思われるが、計器室コックは開になっていたが、特に注意されていなかった。 |
| よもやま話 |
☆ 停電、間違えやすいコックの配置、閉止しておくべきポンプのサクション弁の開放、という事態が重なったため事故に至った。誤操作を招きやすい装置、修理中の安全確保を十分にしておけば事故は防げたといえる。 |
データベース登録の
動機 |
停電時の対処でバルブ操作ミスし爆発した事故例 |
| シナリオ |
| 主シナリオ
|
価値観不良、安全意識不良、リスク認識不良、不注意、理解不足、リスク認識不足、計画・設計、計画不良、工事計画不良、非定常操作、緊急操作、違ったバルブを操作、二次災害、損壊、爆発・火災、身体的被害、死亡、4名死亡、身体的被害、負傷、9名負傷、組織の損失、経済的損失、プラント焼失
|
|
| 情報源 |
通商産業省C石油化学(株)事故調査委員会、C石油化学(株)G工場ポリプロピレン製造装置事故調査報告書(1973)
高圧ガス保安協会、千葉コンビナート保安調査報告書(1978)、p.34-35
北川徹三、爆発災害の解析、日刊工業新聞社(1980)、p.158-160
化学工業協会、事故災害事例と対策、化学プラントの安全対策技術 4、丸善(1979)、p.281-282
|
| 死者数 |
4 |
| 負傷者数 |
9 |
| 物的被害 |
プラント重合設備(ポンプ類,乾燥ブロアー,コンプレッサー類,配管類,重合器,計器パネル,クーラー類,計器類,モーター),ペレット製造設備(ブロアー類,ポンプ類,バルブ類,ドライヤー,押出機,ホッパー類,計器類,建屋),アルデヒド製造設備(配管類)被害.ポリマー,モノマー,n-ヘキサン,水素ガス焼失.付近民家窓ガラス破損9軒,壁の崩れ2軒,窓枠はずれ1軒. |
| マルチメディアファイル |
図2.被災状況図
|
|
図5.化学式
|
|
図6.化学式
|
| 分野 |
化学物質・プラント
|
| データ作成者 |
土橋 律 (東京大学大学院 工学系研究科 化学システム工学専攻)
田村 昌三 (東京大学大学院 新領域創成科学研究科 環境学専攻)
|